
西原台団地自治会
自主防災会

自主防災会たより
平成31年
No85 平成31年 1月 1日
平成30年
No84 平成30年12月26日
No83 平成30年 9月21日
No82 平成30年 8月 6日
No81 平成30年 7月29日
No80 平成30年 6月17日
No79 平成30年 5月 8日
No78 平成30年 4月10日
No77 平成30年 3月10日
No76 平成30年 2月 8日
No75 平成30年 1月22日
平成29年
No74 平成29年12月 5日
No73 平成29年11月 7日
No72 平成29年10月12日
No71 平成29年 9月11日
No70 平成29年 8月15日
No69 平成29年 7月11日
No68 平成29年 6月 5日
No67 平成29年 5月15日
No66 平成29年 4月11日
No65 平成29年 3月 7日
No64 平成29年 2月13日
No63 平成29年 1月18日
平成28年
No62 平成28年12月 6日
No61 平成28年11月10日
No60 平成28年10月12日
No59 平成28年 9月 6日
No58 平成28年 8月 9日
No57 平成28年 7月 5日
No56 平成28年 6月 7日
No55 平成28年 5月10日
No54 平成28年 4月 5日
No53 平成28年 3月 9日
No52 平成28年 2月11日
No51 平成28年 1月 6日
平成27年
No50 平成27年12月10日
No49 平成27年11月 6日
No48 平成27年10月6日
No47 平成27年 9月11日
No46 平成27年 8月 4日
No45 平成27年 7月14日
No44 平成27年 7月14日
No43 平成27年 5月12日
No42 平成27年 4月14日
No41 平成27年 3月 3日
No40 平成27年 2月12日
No39 平成27年 1月 9日
平成26年
No38 平成26年12月 4日
No37 平成26年11月11日
No36 平成26年10月 6日
No35 平成26年 9月 2日
No34 平成26年 8月 5日
No33 平成26年 7月17日
No32 平成26年 6月 5日
No31 平成26年 5月 9日
No30 平成26年 4月 9日
No29 平成26年 3月 8日
No28 平成26年 2月 8日
No27 平成26年 1月 8日
平成25年
No26 平成25年12月 8日
No25 平成25年11月 8日
No24 平成25年10月10日
No23 平成25年 9月 5日
No22 平成25年 8月 7日
No21 平成25年 7月12日
No20 平成25年 6月7日
No19 平成25年 5月 8日
No18 平成25年 4月 5日
No17 平成25年 3月 8日
No16 平成25年 2月12日
No15 平成25年 1月11日
平成24年
No14 平成24年12月10日
No13 平成24年11月 9日
No12 平成24年10月 5日
No11 平成24年 9月 5日
No10 平成24年 8月19日
No09 平成24年 7月12日
No08 平成24年 6月15日
No07 平成24年 5月11日
設置準備委員会たより
平成23/24年
No06 平成24年 4月10日
No05 平成24年 3月 9日
No04 平成24年 2月10日
No03 平成24年 1月13日
No02 平成23年12月 9日
No01 平成23年11月21日
|
自主防災会設置準備委員会たより
(No5) 平成24 年3月9日
(前号)
 (次号) (次号)
【西原町総合防災訓練】
平成24年2月15日(水)09:00 〜 11:00
本訓練は、大地震と大きな津波を想定しての避難訓練でした。
避難訓練内容〜 800 名余の参加者があり、自治会、学校、保育園等が各々の場所からサンエー西原シティー屋上まで避難訓練を実施しました。

訓練には、浦添警察署、東部消防本部、消防団の参加支援もあり、ドクターヘリのデモンストレーションもありました。概ね良好に訓練がなされていました。
【平成23 年度家庭教育学級合同講演会】
〜もし西原町で巨大地震・津波が起きたら〜
平成24年2月20日(月)19:00 〜 21:00 西原町中央公民館大ホールにおいて、講師中村衛琉球大学理学部教授が講演を行いました。

「沖縄県は!"日本一地震の多い地域である」、「過去にも大・津波が発生している」「地震が発生し、大津波が予想された場合は早めに高台に避難すること」「地震のゆれは場所によって違う」等の概要でした。
〜その中で、東日本大震災の例から、数日もの間、孤立化する高いビルよりも出来るだけ陸続きの高台に避難する方が良いとの質疑に対する回答もありました。このことから、津波の襲来に際しては!"かなりの町民等が高台に位置する西原台団地を目指して避難してくることが考えられます。

台団地自治会は、津波情報等で混雑・混乱する中で、これらの避難して来る人々を受け入れ、避難誘導にも対応しなければならない状況になることが予想されます。
「減災」今すくできる「7つの備え」その2
〜 災害被害を少なくする「地域の危険を知る」
【防災マップ(ハザードマップ)】
防災マップは、大地震、津波、台風、洪水などの自然災害が発生した場合の被害のようすや、避難・救援活動に必要な情報が掲載されている地図です。
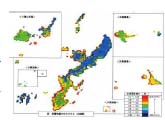
防災マップは、町役場等が作成、配布される事になりますが、西原町では作成に至っていません。台団地自治会独自でも作成すべく危険箇所の把握、資料収集を行っています。
家族みんなで確認しましょう。
【防災ちいき歩き】
「ぼうさいちいき歩き」とは、自分たちの住んでいるちいきを探検して歩き、ちいきの中にある危険な場所を知り、ちいきの中の防災施設などを発見していくものです。
これらを通して地域の歴史を学んだり、防災への関心が高まります。
また、「ぼうさいちいき歩き」で発見したことを地図ハザードマップに書きこむことは、災害に対応するために何をすればよいかを考えるきっかけともなります。他県では子どもたちが作った地図のコンクールも開催されています。
【ゆれやすさ地域の把握】
地震の揺れは、地面のかたさ・やわらかさによって変わります。地面のやわらかいところでは、小さな地震でも大きくゆれます。地面のゆれやすさを示した地図が「ゆれやすさマップ」です。
一般的に高台にある地区は、ゆれにくいと言われていますが、高台では、大雨の時には、地滑り、崩壊の危険もあります。
内閣府の「防災情報のページ」で紹介されていますので、ご自宅やお子さんの通う学校などを、防災マップとあわせて確認してみましょう。
(次号では、今すくできる「7つの備え」その3〜地震に強い家を考察掲載します)
【第2回防災講演会及び報告会】
平成24年3月11日(日)午後2時から中央公民館に於いて開催されます。
ふるって参加しましょう!!
|

