
西原台団地自治会
自主防災会

自主防災会たより
平成31年
No85 平成31年 1月 1日
平成30年
No84 平成30年12月26日
No83 平成30年 9月21日
No82 平成30年 8月 6日
No81 平成30年 7月29日
No80 平成30年 6月17日
No79 平成30年 5月 8日
No78 平成30年 4月10日
No77 平成30年 3月10日
No76 平成30年 2月 8日
No75 平成30年 1月22日
平成29年
No74 平成29年12月 5日
No73 平成29年11月 7日
No72 平成29年10月12日
No71 平成29年 9月11日
No70 平成29年 8月15日
No69 平成29年 7月11日
No68 平成29年 6月 5日
No67 平成29年 5月15日
No66 平成29年 4月11日
No65 平成29年 3月 7日
No64 平成29年 2月13日
No63 平成29年 1月18日
平成28年
No62 平成28年12月 6日
No61 平成28年11月10日
No60 平成28年10月12日
No59 平成28年 9月 6日
No58 平成28年 8月 9日
No57 平成28年 7月 5日
No56 平成28年 6月 7日
No55 平成28年 5月10日
No54 平成28年 4月 5日
No53 平成28年 3月 9日
No52 平成28年 2月11日
No51 平成28年 1月 6日
平成27年
No50 平成27年12月10日
No49 平成27年11月 6日
No48 平成27年10月6日
No47 平成27年 9月11日
No46 平成27年 8月 4日
No45 平成27年 7月14日
No44 平成27年 7月14日
No43 平成27年 5月12日
No42 平成27年 4月14日
No41 平成27年 3月 3日
No40 平成27年 2月12日
No39 平成27年 1月 9日
平成26年
No38 平成26年12月 4日
No37 平成26年11月11日
No36 平成26年10月 6日
No35 平成26年 9月 2日
No34 平成26年 8月 5日
No33 平成26年 7月17日
No32 平成26年 6月 5日
No31 平成26年 5月 9日
No30 平成26年 4月 9日
No29 平成26年 3月 8日
No28 平成26年 2月 8日
No27 平成26年 1月 8日
平成25年
No26 平成25年12月 8日
No25 平成25年11月 8日
No24 平成25年10月10日
No23 平成25年 9月 5日
No22 平成25年 8月 7日
No21 平成25年 7月12日
No20 平成25年 6月7日
No19 平成25年 5月 8日
No18 平成25年 4月 5日
No17 平成25年 3月 8日
No16 平成25年 2月12日
No15 平成25年 1月11日
平成24年
No14 平成24年12月10日
No13 平成24年11月 9日
No12 平成24年10月 5日
No11 平成24年 9月 5日
No10 平成24年 8月19日
No09 平成24年 7月12日
No08 平成24年 6月15日
No07 平成24年 5月11日
設置準備委員会たより
平成23/24年
No06 平成24年 4月10日
No05 平成24年 3月 9日
No04 平成24年 2月10日
No03 平成24年 1月13日
No02 平成23年12月 9日
No01 平成23年11月21日
|
西原台団地自治会自主防災会たより
(No76)平成 30 年 2 月 8 日
(前号)
 (次号) (次号)
「災害は、予兆なしで、突然やって来ます」
〜地球崩壊の壮大な空想〜

災害は、突然に想定外でやって来ることは、これまでの経験則として言われて来ています。
最近の典型的な災害の例としては、1月23日に群馬県草津町の「草津白根山」の突然、3000年ぶりに噴火を起こしたことです。
気象庁は、これまで草津白根山頂付近の火口を24時間体制で観測を続けていたようです。全くノーマークであった山の中腹付近の火口から予兆なく突然噴火してしまったのです。
しかも、草津国際スキー場が近くにあり、ゲレンデ(練習場)にいた利用者に噴石が当たり、訓練中の自衛隊員が死亡、その他負傷者が出たことは報道されました。
また、2014年11月8日の長野・岐阜県堺の御嶽山噴火も突然の噴火で58人の死亡と5人の行方不明者が出たことは、記憶に新しく残っています。(防災イラスト集から)
また、2月5日には、佐賀県神埼市で陸上自衛隊のヘリコプターが住宅に墜落した事故も衆目を集めました。
沖縄県内においても米軍機の墜落事故は、過去にも多く発生しています。
いつでも、突然に空から航空機が降って来るリスクは、どこでもあり得ることなのです。極論を言いますと、隕石が落ちてくるリスクもあるわけです。
2013年2月15日ロシアのチェリャビンスク州で落下した隕石は、死者こそなかったものの、大きな衝撃音と爆風等で多くの家が壊されました。大昔から、大小数えきれない隕石の落下があります。
隕石の落下によって「恐竜が死滅した」との説もあるくらいで、大変な被害をもたらすことが考えられます。
予兆なしで、人類が滅びることは考えられない、考えたくないことなのですが、しかし、遠い遠い将来、何億光年後には、太陽や、地球の寿命が尽きて崩壊していくことを考えると、今の時代、この瞬間に生きていてよかったなと思わざるを得ません。
【応災】(災害対応) 過去の教訓
これからは地震の活動期に我が国は戦後、世界が注目する驚異的な経済成長を遂げました。しかし、この繁栄は「たまたま地震の
静穏期であったから可能だった」と言われています。こうした幸運はいつまでも続くわけはありません。
阪神・淡路大震災は、西日本が地震の活動期に入ったことを示す地震であったと言われ、東日本は、東日本大震災によって不安定要素が増した、とも指摘されています。日本列島が地震の頻発する時代に突入したと言っても過言ではありません。
国民のすべてが「次の震災」に備えることが急務なのです。
阪神・淡路大震災で「共助」が命を救った23年前の1995年1月17日に発生したマグニチュード7.3の地震は死者6,434人を出すという大災害をもたらしました。兵庫県監察医が行った神戸市内の検視によれば、神戸市内の犠牲者3,651人名のうち、83%が窒息し又は圧死で亡くなっています。
また、犠牲者の年齢構成を見ると、3分の1(32.2%)が70歳以上、半数以上(52.7%)が60歳以上という状況になっています。
総合的に見ると、倒壊した木造老朽家屋の一階居住の高齢者に犠牲が集中しています。
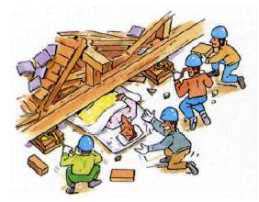
震災後は、特に、建物の耐震性を強化することが地域防災の柱になるとしてクローズアップされました。家屋の耐震化は個人の問題以上に街づくりの課題になりました。
地震防災の観点では、「最も必要な教訓のひとつとして「共助」があげられます。
家屋倒壊によって閉じ込められた人の8割が公助(警察、消防、自衛隊、役場)ではなく、家族や近所の住民によって救出されたのです。(日本防災士会ハンドブックから引用)
|

