
西原台団地自治会
自主防災会

自主防災会たより
平成31年
No85 平成31年 1月 1日
平成30年
No84 平成30年12月26日
No83 平成30年 9月21日
No82 平成30年 8月 6日
No81 平成30年 7月29日
No80 平成30年 6月17日
No79 平成30年 5月 8日
No78 平成30年 4月10日
No77 平成30年 3月10日
No76 平成30年 2月 8日
No75 平成30年 1月22日
平成29年
No74 平成29年12月 5日
No73 平成29年11月 7日
No72 平成29年10月12日
No71 平成29年 9月11日
No70 平成29年 8月15日
No69 平成29年 7月11日
No68 平成29年 6月 5日
No67 平成29年 5月15日
No66 平成29年 4月11日
No65 平成29年 3月 7日
No64 平成29年 2月13日
No63 平成29年 1月18日
平成28年
No62 平成28年12月 6日
No61 平成28年11月10日
No60 平成28年10月12日
No59 平成28年 9月 6日
No58 平成28年 8月 9日
No57 平成28年 7月 5日
No56 平成28年 6月 7日
No55 平成28年 5月10日
No54 平成28年 4月 5日
No53 平成28年 3月 9日
No52 平成28年 2月11日
No51 平成28年 1月 6日
平成27年
No50 平成27年12月10日
No49 平成27年11月 6日
No48 平成27年10月6日
No47 平成27年 9月11日
No46 平成27年 8月 4日
No45 平成27年 7月14日
No44 平成27年 7月14日
No43 平成27年 5月12日
No42 平成27年 4月14日
No41 平成27年 3月 3日
No40 平成27年 2月12日
No39 平成27年 1月 9日
平成26年
No38 平成26年12月 4日
No37 平成26年11月11日
No36 平成26年10月 6日
No35 平成26年 9月 2日
No34 平成26年 8月 5日
No33 平成26年 7月17日
No32 平成26年 6月 5日
No31 平成26年 5月 9日
No30 平成26年 4月 9日
No29 平成26年 3月 8日
No28 平成26年 2月 8日
No27 平成26年 1月 8日
平成25年
No26 平成25年12月 8日
No25 平成25年11月 8日
No24 平成25年10月10日
No23 平成25年 9月 5日
No22 平成25年 8月 7日
No21 平成25年 7月12日
No20 平成25年 6月7日
No19 平成25年 5月 8日
No18 平成25年 4月 5日
No17 平成25年 3月 8日
No16 平成25年 2月12日
No15 平成25年 1月11日
平成24年
No14 平成24年12月10日
No13 平成24年11月 9日
No12 平成24年10月 5日
No11 平成24年 9月 5日
No10 平成24年 8月19日
No09 平成24年 7月12日
No08 平成24年 6月15日
No07 平成24年 5月11日
設置準備委員会たより
平成23/24年
No06 平成24年 4月10日
No05 平成24年 3月 9日
No04 平成24年 2月10日
No03 平成24年 1月13日
No02 平成23年12月 9日
No01 平成23年11月21日
|
西原台団地自治会自主防災会たより
(No66)平成 29 年 4 月 11 日
(前号)
 (次号) (次号)
【246 年前の4 月24 日発生の”明和の大津波”】
<<石垣市大浜崎原公園内の「津波岩」)>>
 八重山・宮古地方で津波による犠牲者は約1 万2 千人。
八重山・宮古地方で津波による犠牲者は約1 万2 千人。
八重山地震津波とも言われ、1771 年4 月24 日(旧暦3 月10日)午前8 時頃に発生しました。地震の震源は石垣島南東沖、
マグニチュードは8.5 を超えたとの説もあります。地震の揺れは沖縄本島周辺でも感じられたと記録に残されています。
地震の揺れの直後、各地を大津波が襲いました。津波の遡上高(陸を駆け上った高さ)は、石垣島南東部から東部海岸で30m以上、多良間島で18m、宮古島周辺で約10m 程度と推定されています。沖縄本島周辺でも潮の流れが異常になったことが記録に残っているので、小さい津波が沖縄本島付近まで押し寄せたようです。
津波による死者は、八重山諸島で9,313 人、宮古地方で2,548人との記録があります。(死者や被害の状況が詳細に残っているのは、当時の人頭税で蔵元庁舎や地域の番所に地域ごとの人口が細かく記帳把握されていたのです。これらの古文書は、国内での津波に関する貴重な第一級の資料と言われています。)
 <<(宮古島市下地島世界最大の津波岩「帯岩」)>> <<(宮古島市下地島世界最大の津波岩「帯岩」)>>
当時作成された『大波之時各村之形行書』(おおなみのときかくむらのなりゆきしょ)によると、石垣島における津波の最大遡上高は、宮良村で「二十八丈」84.8m に達したと記録されていますが、専門家の研究で84.8m の津波は否定されています。
東京大学の専門家の研究では、150 年から400 年の周期で大きな津波が押し寄せてきていることが解明されているようです。これらの津波は地殻変動による地震の結果発生します。先月の「防災たより65 号」でもお知らせしたとおり、沖縄周辺では陸地と言わず、海と言わずあっちこっちで有感・無感の地震が年間1万件以上発生しています。私たちは、「いつかは必ず大きな地震と津波がやって来る」ことを認識しておくことが必要です。
【災害への備え~防災マニュアル家族編~】
避難所は快適ではありません( 1 ) !?
災害時の避難所は、ほとんどが学校・体育館や公共施設に設けられます。
長引く避難所の生活は、「ダンボールついたて」や「カーテン」等が用意されることがありますが、冬場は、床が冷え、生活する上で食事、風呂、洗濯は思うように出来ず、石けん、ウエットティッシュ、洗面用具、歯磨きセットのような衛生用品は不十分です。
トイレは大行列ができ、繰り返される揺れ等への不安から睡眠不足になり、病気、体の不自由な人、年配の方が周囲に気兼ねをします。衛生上の問題からウイルス感染にかかりインフルエンザや食中毒にかかってしまうことも。
また、避難所の収容能力には限界があります。せいぜい住民の10%程度しか収容できません。昨年の熊本地震では車中泊の避難者が目立ちました。一度は避難所へ避難し、落ち着いてからは自宅で過ごすのが一番です。もちろん、自宅が無事であればのことです。
自家用車で寝泊まり出来る備えをしておくのも必要なことです。
【防災に対する住民の意識は3つのタイプ】
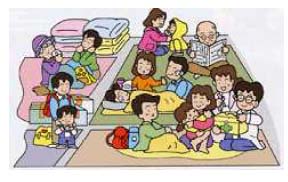 ①「防災を意識し、実際に防災対策の行動に移している住民」
①「防災を意識し、実際に防災対策の行動に移している住民」
②「防災は意識しているが、防災の行動には移せていない住民」
③「防災にまったく関心がない住民」
さあ、あなたはどのタイプ? 私達は、日頃から、できる範囲で防災対策を進めましょう!
|

