
西原台団地自治会
自主防災会

自主防災会たより
平成31年
No85 平成31年 1月 1日
平成30年
No84 平成30年12月26日
No83 平成30年 9月21日
No82 平成30年 8月 6日
No81 平成30年 7月29日
No80 平成30年 6月17日
No79 平成30年 5月 8日
No78 平成30年 4月10日
No77 平成30年 3月10日
No76 平成30年 2月 8日
No75 平成30年 1月22日
平成29年
No74 平成29年12月 5日
No73 平成29年11月 7日
No72 平成29年10月12日
No71 平成29年 9月11日
No70 平成29年 8月15日
No69 平成29年 7月11日
No68 平成29年 6月 5日
No67 平成29年 5月15日
No66 平成29年 4月11日
No65 平成29年 3月 7日
No64 平成29年 2月13日
No63 平成29年 1月18日
平成28年
No62 平成28年12月 6日
No61 平成28年11月10日
No60 平成28年10月12日
No59 平成28年 9月 6日
No58 平成28年 8月 9日
No57 平成28年 7月 5日
No56 平成28年 6月 7日
No55 平成28年 5月10日
No54 平成28年 4月 5日
No53 平成28年 3月 9日
No52 平成28年 2月11日
No51 平成28年 1月 6日
平成27年
No50 平成27年12月10日
No49 平成27年11月 6日
No48 平成27年10月6日
No47 平成27年 9月11日
No46 平成27年 8月 4日
No45 平成27年 7月14日
No44 平成27年 7月14日
No43 平成27年 5月12日
No42 平成27年 4月14日
No41 平成27年 3月 3日
No40 平成27年 2月12日
No39 平成27年 1月 9日
平成26年
No38 平成26年12月 4日
No37 平成26年11月11日
No36 平成26年10月 6日
No35 平成26年 9月 2日
No34 平成26年 8月 5日
No33 平成26年 7月17日
No32 平成26年 6月 5日
No31 平成26年 5月 9日
No30 平成26年 4月 9日
No29 平成26年 3月 8日
No28 平成26年 2月 8日
No27 平成26年 1月 8日
平成25年
No26 平成25年12月 8日
No25 平成25年11月 8日
No24 平成25年10月10日
No23 平成25年 9月 5日
No22 平成25年 8月 7日
No21 平成25年 7月12日
No20 平成25年 6月7日
No19 平成25年 5月 8日
No18 平成25年 4月 5日
No17 平成25年 3月 8日
No16 平成25年 2月12日
No15 平成25年 1月11日
平成24年
No14 平成24年12月10日
No13 平成24年11月 9日
No12 平成24年10月 5日
No11 平成24年 9月 5日
No10 平成24年 8月19日
No09 平成24年 7月12日
No08 平成24年 6月15日
No07 平成24年 5月11日
設置準備委員会たより
平成23/24年
No06 平成24年 4月10日
No05 平成24年 3月 9日
No04 平成24年 2月10日
No03 平成24年 1月13日
No02 平成23年12月 9日
No01 平成23年11月21日
|
西原台団地自治会自主防災会たより
(No80)平成 30 年 6 月 17 日
(前号)
 (次号) (次号)
「巨大災害が国の存立・発展に致命的な影響」
(土木学会発表を考える)
去る6 月7 日、土木学会(大石久和会長)は『国難』をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告書」をとりまとめ公表しました。
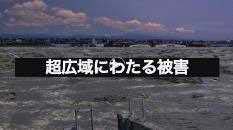
南海トラフ地震・津波や大都市河川大洪水等の「国難的災害」に対して、巨大災害が起こっても致命的事態を回避し、その被害を回復可能な範囲にとどめ得る対策、すなわち「国土のレジリエンス」確保方策を示すための議論を行っており、これらをとりまとめたものです。
(※レジリエンスとは:一般的に「復元力、回復力、弾力」などと訳され、近年は「困難な状況で、しなやかに適応して生き延びる力」という意味に使われている。)。
大石会長によりますと、「今のままで巨大災害が起きたら想像もつかないようなことになる。日本が東アジアにおける小国、最貧国のひとつになりかねないと考えている」と述べ、各方面に反響を呼びました。。
その“危機感”のポイントのいくつかを取り上げますと、
〇わが国は世界有数の自然災害地、そこに高度・高密な産業活動が集積。
この地を巨大自然災害が襲えば、その被害は国の存立・発展に致命的なな影響を及ぼしかねない(内閣府資料から)。
○ 過去の大災害がもたらした長期的影響を調査、これをもとに今後起こりうる巨大災害のもたらす被害を推計し、それを減ずるに必要な対策とその経済的効果を示して対策の早期実施を求めた。
○ 旧来の防災インフラ以外の制度的、教育啓蒙的な対策の早期実施、新規防災財源の創設提言。
○ 巨大災害は余りにも膨大で、私たちの能力や時間は限られる。そのため「南海トラフ地震」等のみを検討対象とし、また対策・効果の推定も堤防、道路等公的インフラの整備・増強に限定した。
○ 報告の被害推計の特徴は「長期的な経済被害」にある。地震については20年、水災害については14カ月の経済低迷効果をシミュレートし、経済被害を推計した。
● 「長期的な経済被害」として〜南海トラフ地震で20年間の被害推計は、最大1,410兆円(2018年度国の一般会計予算(97兆7千億円)の14年分!)。
発災すれば、「最貧国になりかねない」、「会社だと赤字で倒産するが、国の場合は滅亡する」という発言も衝撃的なものでした。このことから、為政者もそして地域に住む私達も災害対応、防災をこれまで以上に考え、取り組まなければならないとの思いに駆られました。。
南海トラフ地震や首都圏直下型地震は近い将来必ず来る!と言われていますが、こればかりは分かりません。沖縄東方沖地震が先かも知れませんし、南海トラフ地震との連動地震になるのかも知れません。
今、高齢化社会の中にあって、65 歳以上が人口に占める割合が21 %を超えると超高齢化社会と言われていますが、私達西原台団地自治会もまさに「超高齢化社会」とも言えます。
これからの地域における防災活動をどのように取り組んでいくのか大変悩むところです。
自治会会員皆さんの自治会活動、防災活動への積極的な参加をお願いします!
「沖縄のゆいまーる精神」(一口メモ)


地域防災は自助・共助が中心で、「住んでいる地域を知る」、「その地域の自然を正しく理解し、災害を知る」、そして「私たち自身を知る」ことが必要なことです。
その上で、「顔の見える人間関係をつくり、コミュニティレベルで相互協力体制を確立すること」、「震災から学んだ教訓を生かすこと」が大切です。
沖縄の文化でもある「ゆいまーる精神」は、いわば、「結」(協同・協働)の精神で見返りはなく、順番に公平に相互扶助を行うというもので、かって地域がまとまりコミュニティ社会が出来上がっていました。
それが今や形骸化しつつあります。
「防災の基本」は自助、共助、コミュニケーションづくりです。
ご近所は、ご近助するものです!
※「災害は、いつでも、どこでも、突然に、想定外で発生する」日頃から備えよう!
|

